 研究・教育
研究・教育
高等学校の科目保健の時間に、健康のとらえ方の学習をしたと思います。WHO(世界保健機関)は精神的・身体的・社会的に満たされていればそれが健康であるといわれていますが、現在は、その3つの輪に4つ目の輪「生きがい」が加わっています。高齢の方、体のご不自由な方、など、社会には体の強い人も弱い人もいてお互いに認め合って共生社会を作っています。
みんなが生きやすい共生社会を作る意識がとても大切だと思います。高等学校で学んだ知識を大学で「生きた知識」にできるように理論的に学んでいきましょう。
私は、前職が公立学校で36年間養護教諭をしていました。保健室には、けがや病気以外にも、学校に来ることがつらくなった生徒や困った出来事があったり、寂しくなったりした生徒がたくさん来ました。
1日に50人以上の生徒が来る日もあります。他人にとっては些細なことも、本人にとってはひどくつらい心になったりします。心と体の相関関係があるので、それを敏感に感じ取れる教員を養成したいと思いました。 体育大学だから、みんな強い心を持っているだろうと思いがちですが、みんな同じです。
自分の弱さを表現できる生徒、助けてを生徒が言ったときに、手を差し伸べることができる先生を養成したいと思っています。
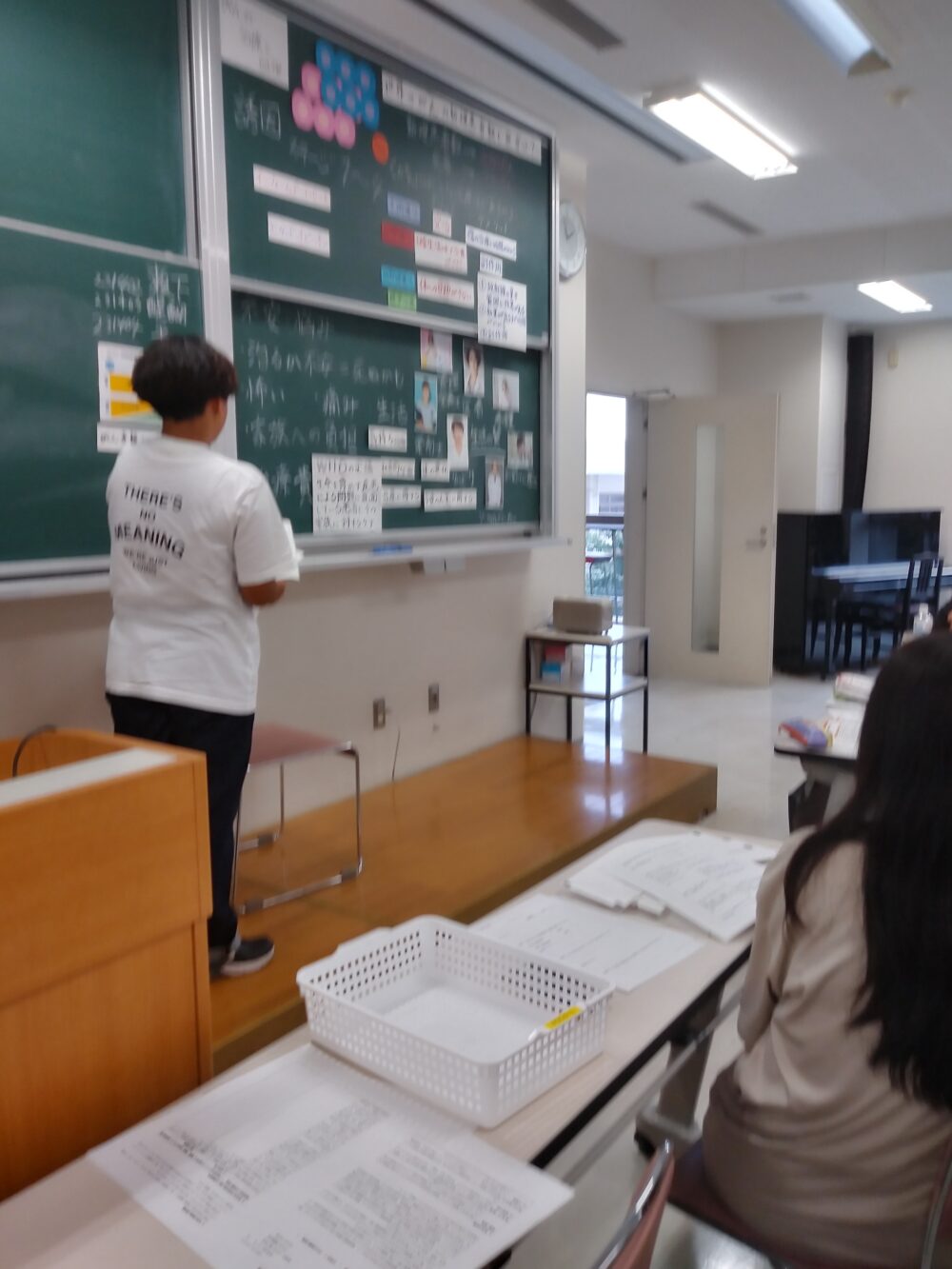
模擬授業
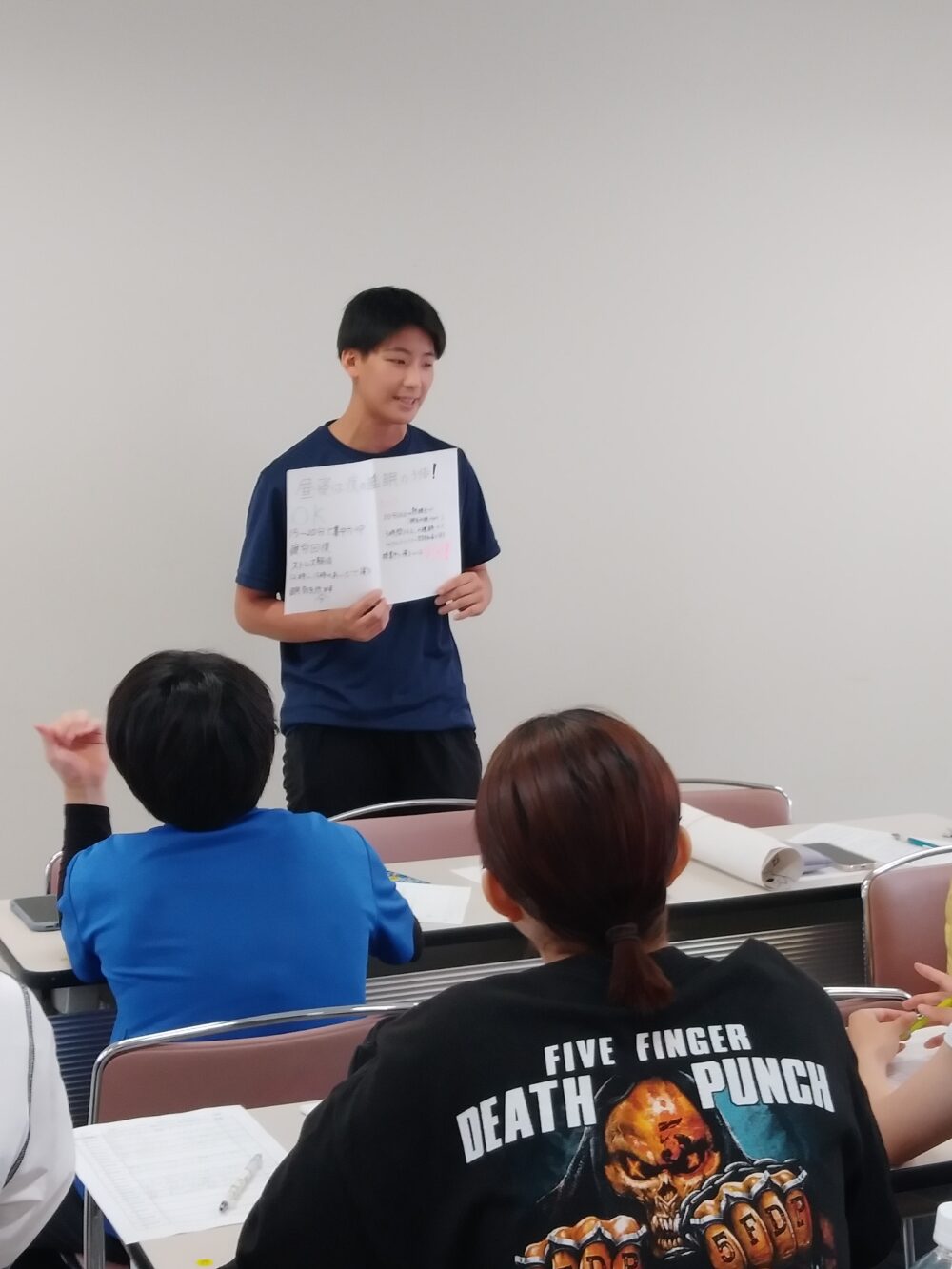
5分間保健指導
「健康教育研究室」は、テーマは何でも大丈夫です。それは、健康はすべてにつながっているからです。
卒業研究のテーマは、自分が興味のあることでないと2年間モチベーションをもって研究できません。
自分の興味関心のあるテーマを見つけることが一番大事だと思います。ただ、健康教育研究室は、健康に対して高い価値観を持つ人を求めています。
ONとOFFは大事にします。
卒業研究の指導が、私はとても好きです。ゼミ生が興味のあることを調べ、考えたことを私に教えてくれます。それがとても面白いです。なので、毎年12月の卒業研究発表会が終了すると、とてもほっとするのと同時に、ゼミ生と研究を進めていたことを手放すかと思うととても寂しく、複雑な日が卒業研究発表会の日です。
私の卒業研究の指導は、計画的に行い、発表の2週間前には必ず、リハーサルをします。どんなことも事前準備が大切です。あわてて何かをするということはしません。余裕をもって、自分の研究を皆さんに表現できる発表会は、社会に出てもとても役に立つ場だと思っています。その準備のお手伝いをやるのが教員です。
「保健科教育」はカリキュラム改定が8年度からありますが、7年度までは「保健指導研究」という教科名です。教職必修の中学校・高等学校教諭免許(保健)科目「保健科教育」を担当して8年目です。
1クラス100名で3クラス300名の学生に、半期15コマで学習指導要領の理解から指導案の作成、また全員の模擬授業を実施しています。中学校・高等学校のすべての単元を3クラスの学生に割り振り、3人のグループを作り、模擬授業を展開するという方法でやっています。3人それぞれの同じ単元の指導案を持ち寄って、模擬授業を実施しますが、指導案検討の時間が取れないため、私の授業外の時間を30分づつの予約制にして研究室で指導案検討から教材の作り方、授業方法について個別指導を実施して、やっと50分の授業ができます。私の空き時間がすべて学生との指導案検討になり、きつい面はありますが、学生が「なるほど」「そうか」と知識の理解と生徒に授業をすることへの意欲や面白さを感じてくれることに大きな喜びを得ています。

模擬授業風景
私は、保健科の授業づくりがとても好きです。教育実習で保健科の授業を実施し、「褒められた」「保健の授業がとても面白い」と言ってくれると、本当にやりがいを感じています。保健科は、予防教育でかなりの広範囲です。穴埋めの授業や教科書の音読の時間にはしません。保健科をする目的は、「国民の健康の教養を高めることと、将来健康問題が起きたときの問題解決の方法を学ぶことです。 社会の要請にこたえる科目でもあります。
薬事法が改正されれば、「薬の適正使用」の単元ができ、がんが2人に一人という状態になれば「がん教育」の単元が入ります。現在の学習指導要領には、精神疾患の特徴、予防、回復の単元が入りました。これは15歳ごろが精神疾患の好発年齢であることや15歳から39歳までの死亡の第1位が「自殺」である実態から、高校で学ぶことになりました。逆に言えば、それだけ体育教員への期待、保健科への期待が大きいということになります。
他には「学校保健」の教科では、学校保健の歴史はもちろんですが、5分間保健指導発表会、緊急時の対応をロールプレイングで9名の役割を実践したり、アナフィラキシー発症時のエピペンの打ち方の体験など、実践力を高める授業としています。
「学校とスポーツの安全」の授業では、毎回裁判事例から学び、自分の考えを記述する授業としています。

卒業研究発表会①

卒業研究発表会②
とても仲良し!
写真を見ていただければわかりますが、3年生のゼミ開講の時は、同じクラスでなければ話したこともない学生同士で、緊張していましたが、卒業研究をするうちに助け合い、励まし合って目的に向けて頑張れるゼミ生達です。日本女子体育連盟研究発表会が毎年2月にありますが、今年も3名の学生に参加してもらいました。
国立オリンピック青少年会館で自分の研究をポスター発表しました。次の3つが卒業研究のテーマで、発表してきました。他大学の教員からも質問を受け、堂々と答えている姿に頼もしさを感じました。3人の研究タイトルです。
「女子体育大生のeスポーツの関心に関する研究」 「ラグビーの「地域密着型」への取り組みに関する研究ー東芝 ルーパス塾へのインタビュー調査を通してー」「自然体験活動の応急手当てに関する研究」 自分の興味関心で選んだ研究テーマでした。
これまでのゼミ生の学外での活動はいろいろありました。整形外科の医師の講演会で、実技の演技をしたり、特別支援教育の研究テーマの学生を近隣の小学校に1年間通って、対象児童の観察をしたり、また、月経指導を小学校でやらせていただいたりしました。
教員には実践力が必要です。本で調べるだけでなく、実際に学校というフィールドで体験しながら目的をもって学ぶことが大事だと思います。現在は、私の研究で高等学校で、精神疾患の授業研究をしていて、ゼミ生に授業の撮影などで手伝ってもらっています。今年度ゼミ生は2回高校に行きました。
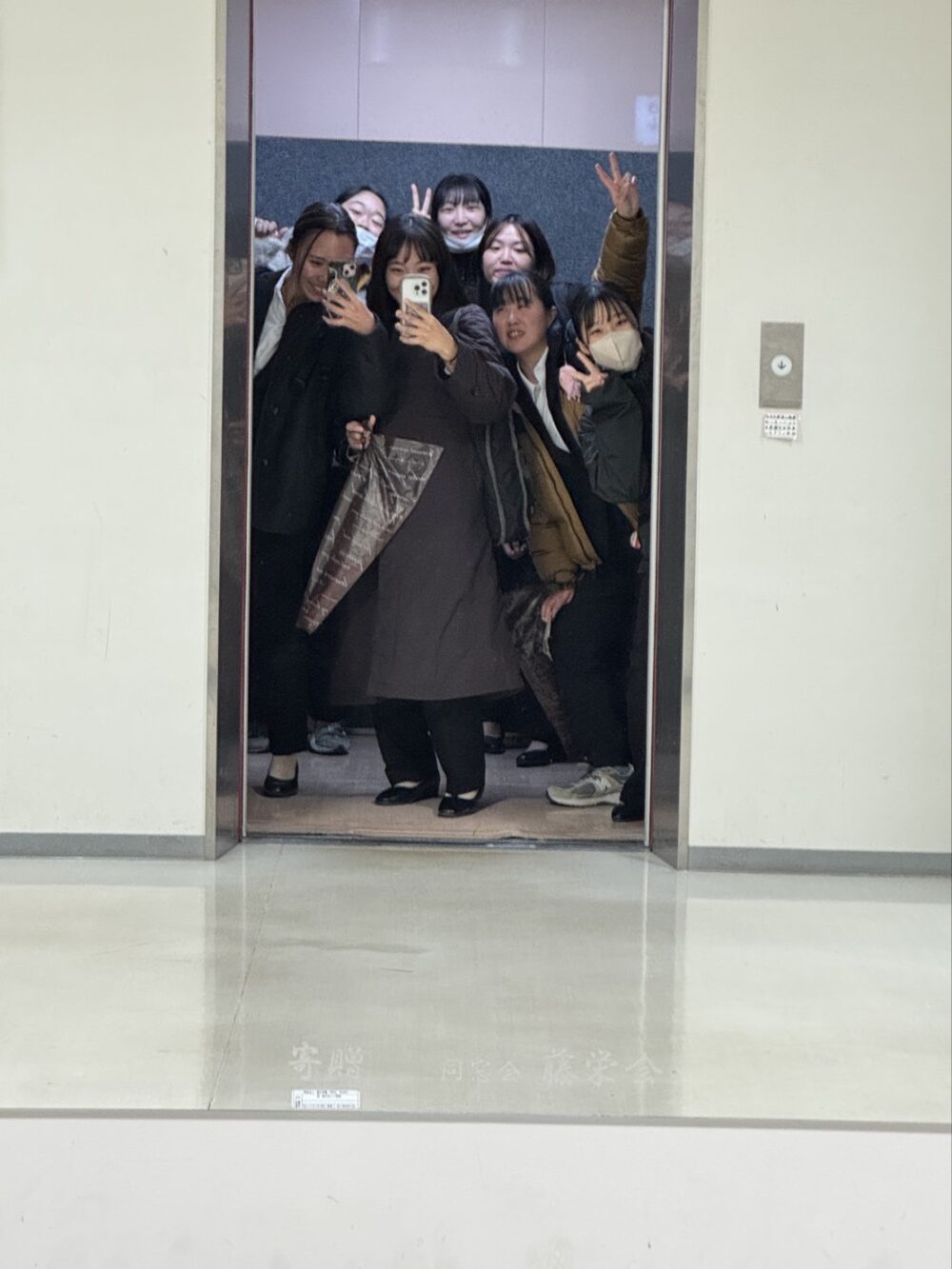
みんな仲良し

胸骨圧迫実習中
私の授業は、教職必修ですが、将来教員にならない学生でも、全く問題ありません。 「なりたい」自分を大学でぜひ探してください。
それには、自己理解をすることです。授業は、ただ単位を取ればいいということではなく、研究をすることが大学では求められます。本学の創始者の藤村トヨ先生は、100年前にそのことを言っています。また、本学の卒業生は、非認知能力がとても高いです。非認知能力とは、数字で表せない能力のことです。
「一生ものの姿勢をつくる」が本学のコンセプトメッセージです。ぜひ本学で生き方を考えていただきたいと思っています。
保健科教育では指導案を作成するだけでなく、実際に授業をやって、それを振り返って、どこが上手くいったのか、どこができなかったのか、それを省察する力をつけてもらいたいと思います。
高柳佐土美、1959年 大分県生まれ
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 教授
千葉大学大学院教育学研究科学校教育科学修士課程修了 (教育学修士)
主要学科目は保健科教育・学校保健・学校とスポーツの安全

2025.02.06

2026.01.16

2025.12.23